2007年10月24日
鞍馬の火祭り
11月22日、市内では時代祭りでにぎわっていますが、その夜山深い鞍馬寺では火祭りが行われます。
京の三奇祭の一つ「鞍馬の火祭り」は千年以上続く由緒あるお祭りです。しかし、経費の問題や人手不足の問題で何度か存続の危機に立ち、現に昭和53年には一度中断してしまいましたが、鞍馬の人々の祭りに掛ける意気込みで翌年再び行われるようになりました。
今回2回目の訪問ですが、以前には感じなかった地元の人たちの思いがひしひしと伝わってきました。
貴船口までタクシーで、そこからは鞍馬まで徒歩で行きます。街道沿いの家々ではさまざまなしつらえがされています。メインの松明も大きいのやら小さいのやら。鎧の飾りにの前にはなぜか生姜と大根がお供えされています。


この松明を担ぐ男の子、小さい頃から、いや母のお腹の中にいるときから祭りの空気を吸って大きくなってきた子どもたち、文化や伝統はこうして引き継がれていくのでしょうね。

京都のお祭りならではの剣鉾(祇園祭の鉾の原型)。面白いのは天狗の面が付いていること。鞍馬の天狗を現しているのでしょうか?

祭り飾りの前で記念撮影させていただきました。
お宮から出された神輿の前、ご神火がかがり火に灯され、いよいよ祭りの始まりです。

この後、家々から松明が「さいりょう さいれい」の掛け声とともに街道を練り歩きます。最初は子どもたちがきれいな模様の長襦袢を上に羽織った上に松明を担いで練り歩きます。中には3歳ぐらいの子どもも。

見物客からは思わず拍手が・・。こういう経験を小さい頃にするとやめられませんね。
京の三奇祭の一つ「鞍馬の火祭り」は千年以上続く由緒あるお祭りです。しかし、経費の問題や人手不足の問題で何度か存続の危機に立ち、現に昭和53年には一度中断してしまいましたが、鞍馬の人々の祭りに掛ける意気込みで翌年再び行われるようになりました。
今回2回目の訪問ですが、以前には感じなかった地元の人たちの思いがひしひしと伝わってきました。
貴船口までタクシーで、そこからは鞍馬まで徒歩で行きます。街道沿いの家々ではさまざまなしつらえがされています。メインの松明も大きいのやら小さいのやら。鎧の飾りにの前にはなぜか生姜と大根がお供えされています。
この松明を担ぐ男の子、小さい頃から、いや母のお腹の中にいるときから祭りの空気を吸って大きくなってきた子どもたち、文化や伝統はこうして引き継がれていくのでしょうね。
京都のお祭りならではの剣鉾(祇園祭の鉾の原型)。面白いのは天狗の面が付いていること。鞍馬の天狗を現しているのでしょうか?
祭り飾りの前で記念撮影させていただきました。
お宮から出された神輿の前、ご神火がかがり火に灯され、いよいよ祭りの始まりです。
この後、家々から松明が「さいりょう さいれい」の掛け声とともに街道を練り歩きます。最初は子どもたちがきれいな模様の長襦袢を上に羽織った上に松明を担いで練り歩きます。中には3歳ぐらいの子どもも。
見物客からは思わず拍手が・・。こういう経験を小さい頃にするとやめられませんね。
この後、独特の衣裳を着けた大人が松明を担いで何度も何度も行き来しました。

それはそれは勇壮で優雅。
そして・・・クライマックスには大松明がいっせいに山門まえの階段に勢ぞろい。火の粉が掛かるのもお構い無しに、体を左右に揺らしながら「さいりょう さいれい」と・・・そして次々に松明が石段下に投げ込まれていきます。
そして神輿が石段を下ろされてきます。今回はここまで見て帰りましたが、いつか最後まで見て見たい物です。
それはそれは勇壮で優雅。
そして・・・クライマックスには大松明がいっせいに山門まえの階段に勢ぞろい。火の粉が掛かるのもお構い無しに、体を左右に揺らしながら「さいりょう さいれい」と・・・そして次々に松明が石段下に投げ込まれていきます。
そして神輿が石段を下ろされてきます。今回はここまで見て帰りましたが、いつか最後まで見て見たい物です。
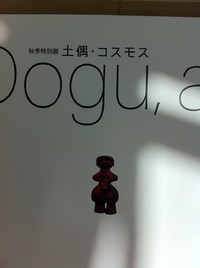






鞍馬の火祭りに行ってこられたんですね。
羨ましいです。
でも、鞍馬の夜は相当冷え込んだでしょう。
学生時代は毎年行っていたんですが、
このところは行けなくて。。。
煤で真っ黒だったお神輿も、今年修理されて、ピカピカになっていますね。
結構、祭好きなモンですから、特に画像を上げておられる、「剣鉾」にはまってまして、
あの天狗の面は、どこのお祭の行列にも出てくる、大榊に天狗の面=猿田彦神を表わしていると思います。
その猿田彦と剣鉾が合体した姿じゃないでしょうか。
剣鉾が神輿を護り、邪気を祓う役目をするのと似ていて、
猿田彦神は、神輿の進む先を行って、先導役を務めます。
秋の火祭りは、これから厳しい冬を控えて、
何かしみじみと、自然の恩恵に感謝するひと時を、
噛みしめることが出来ますね。
剣鉾は全部で7本あるそうです。そのうち上と下に一本つづ大きな剣鉾があり、4人掛かりで持ち上げます。
市中よりもうんと寒い中、それでも火のそばは温かく、火の恩恵を感じれるお祭りでした。
ずんずんさんは学生時代に毎年行かれていたそうですが、最後までご覧になったのでしょうか。遅くなってしまうので、神輿が降りると早々に引き上げてしまうので、その後どうなるのかわかりません。聞くところによるとまだまだ色んな行事があるようですね。出来れば一度最後まで見てみたいと思います。
二基の神輿はその後鞍馬温泉まで行って戻ってきます。
そして、鞍馬の集落の下手にあります御旅所に駐輿されます。
神輿が納まると、大きな焚き火を中心に、そこらに居る人々皆に、
お神酒が振舞われます。
酒の肴ならぬ、お神酒の肴に、するめ等も頂けて、
炎を眺めながら、火祭りの余韻に浸って、しみじみとお神酒を味わうのです。
結構お代わりなどして、良い加減になって、寒さもどこへやら。
深夜の3時ころになって、学生時代は友達の下宿の市原まで歩いて帰ったものです。
ねっ!結構いいでしょ。
あの2基の神輿は、お旅まで戻ってくるのですね。お神酒とするめがみんなに振舞われるのも、和やかでいいですね。
こんな話を聞くと最後まで痛くなりますね。こんどは思い切って最後まで居ようかな・・
それもいいですね。
そうか、若い子がこれから行くのが不思議でしたが、お神酒ね・・。
でも、みんなに振舞われるなんて、それこそお祭りらしくていいですね。
来年がんばりますか。