2006年12月12日
「謡講」特別バージョン
しばらく忙しくて書き込みもままならない状況でしたが・・。
3日の日曜日は「謡講」の特別バージョンがありました。苔寺の近くの「苔香居」という、非公開の庄屋さんで、登録文化財に指定されている建物で、庭の紅葉を見ながら謡を聞いたり、いつもの様に薄暗い中で謡を聞いたり、みんなでお食事をしたりと、普段出来ない参加者同士の交流も出来て、とっても楽しい一日でした。

井上裕久先生による解説からはじまり・・・

宴席では、今はめづらしくなったお座敷での余興の一つが披露されました・・そして時間を忘れての歓談・・・苔香居の座敷も久々ににぎやかさを取り戻して、生き生きとした表情を取り戻しました。
「謡講」はいつもは一参加者として拝聴するだけですが、今回の会場の「苔香居」は管理のお手伝いをさせていただいている関係で、半分裏方として参加させていただきました。普段経験する事のない「謡講」の裏側を見させていただきました。
「苔香居」は現在の当主が20代目の方で、建物も江戸期から明治期の町家ですが、庄屋をされていた関係で囲炉裏もあり、またおくどさんもまだ残っています。また、幕末期から現在までの着物が約380点ほどあり、特に大正にこのお宅にお嫁に来られた方の婚礼衣装などがすばらしいものがあります。それらも今回一部ご覧いただきました。
ちなみに謡講の通常バージョンがこの16日(土)に高台寺の塔頭「春光院」で2時と5時に行われます。ぜひどうぞお越し下さい。
3日の日曜日は「謡講」の特別バージョンがありました。苔寺の近くの「苔香居」という、非公開の庄屋さんで、登録文化財に指定されている建物で、庭の紅葉を見ながら謡を聞いたり、いつもの様に薄暗い中で謡を聞いたり、みんなでお食事をしたりと、普段出来ない参加者同士の交流も出来て、とっても楽しい一日でした。
井上裕久先生による解説からはじまり・・・
宴席では、今はめづらしくなったお座敷での余興の一つが披露されました・・そして時間を忘れての歓談・・・苔香居の座敷も久々ににぎやかさを取り戻して、生き生きとした表情を取り戻しました。
「謡講」はいつもは一参加者として拝聴するだけですが、今回の会場の「苔香居」は管理のお手伝いをさせていただいている関係で、半分裏方として参加させていただきました。普段経験する事のない「謡講」の裏側を見させていただきました。
「苔香居」は現在の当主が20代目の方で、建物も江戸期から明治期の町家ですが、庄屋をされていた関係で囲炉裏もあり、またおくどさんもまだ残っています。また、幕末期から現在までの着物が約380点ほどあり、特に大正にこのお宅にお嫁に来られた方の婚礼衣装などがすばらしいものがあります。それらも今回一部ご覧いただきました。
ちなみに謡講の通常バージョンがこの16日(土)に高台寺の塔頭「春光院」で2時と5時に行われます。ぜひどうぞお越し下さい。
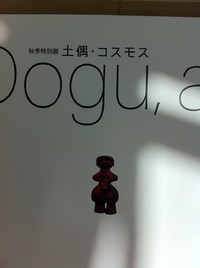






そして、素敵な一日をありがとうございました。
想像以上に素晴らしいお屋敷で、謡を聞き、お酒も飲んで、
贅沢!
謡講いいですね、やっぱり高台寺にも行きたくなってしまった、、、。
高台寺、演目も一部は「鉢木」二部は「景清」とどちらも聞かせどころの多い名曲中の名曲。この時期にはもってこい。ぜひ ぜひ・・お越し下さい。今回は定員はありませんから。